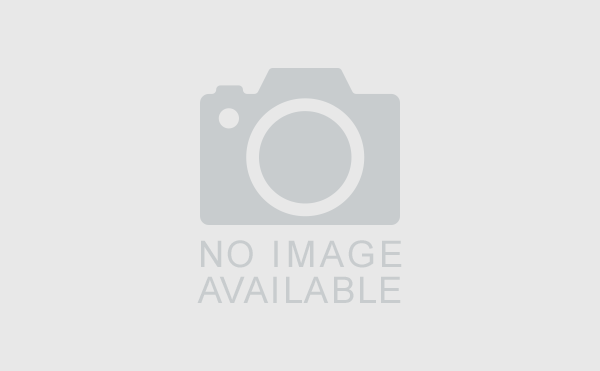博多の陥没事故現場の埋め戻しは流動化処理工法だったらしい(今さらながら知った)
1.博多の陥没事故の復旧工は流動化処理工法が用いられた。
それにしても地盤を相手に仕事している人間が、「流動化処理土」を知らないって、恥ずかしいなあと思った次第です。


【博多駅前陥没】オール福岡「強度30倍」わずか1週間で復旧 雨で通行再開15日ずれ込み(1/2ページ) – 産経WEST
だいぶ前の記事になりますが、「以前の30倍の強度の地盤が工事でできた」というコメントがよく解らないでおりました。
解せないなあとずっと思っていたのですが、先日、とある講習会で「流動化処理工法」という話を伺った。
「流動化処理土」とはどんなもの? « 流動化処理工法研究機構
博多陥没事故の埋め戻しの中継で「ミキサー車」がいっぱい映っていたが、それはコンクリートを搬入していたわけではなく、「流動化処理土」を搬入していたとのこと。
この工法が採用された理由は以下の通り。(走り書きでメモってきたので、怪しい部分有り。)
1. 水中施工が可能である。
2.複雑な空洞形状に充填できる。
3.早期施工が可能である。
4.かちこちに固結しないので再掘削が可能である。
5.材料確保が容易で多量に入手できる。
6.隙間に入りやすい特性がある。
7.人が現場に立ち入らなくても施工が可能である。
そういう訳で、あの事故の復旧には「流動化処理工法」以外考えられなかったそうです。
2.流動化処理土とは
流動化処理土とは、盛土材料としては、あまり使いたくないシルトや粘土に対して、泥水や固化剤などを混ぜたリサイクル材料とのこと。
埋め戻す時は、液状の材料であり複雑な形状の所にも隙間無く埋め戻しが可能である。
投入一日後には、人が歩けるくらいの固化が進んでいる。
その一方、4週間後においても、コンクリートのようにかちこちに固結するわけでもなく、人力(スコップ)で掘り起こす事も可能である。
固化剤などの調整によっては、バックホーで掘削する強度などにも調整ができる。
一軸強度200kN/m2くらいから任意設定ができる。
工場プラントからの運搬でも現場プラントを作ることも施工可能。
特許管理は、独立行政法人 土木研究所。(品質維持確保のため)
3.流動化処理土法の利点
(1)空間の埋戻し・裏込
(2)土のリサイクル
・締固め不要の埋戻し
・ポンプ圧送が可能
・水中でも打設が可能
・強度コントロールが可能(一般に再掘削が可能)
・液状化はしない
・材料分離が少ない
4.施工事例
・構造物の埋戻し
・地下駐車場の埋め戻し
・廃止ボックスカルバートの埋戻し
・大型構造物解体時の地下充填
・地下鉄地下構造物の埋戻し
・道路下空洞充填(陥没事故など)
・護岸空洞充填
・廃坑の充填
・道路拡幅における盛土施工
・パイプライン埋戻し
一部、配付資料を写しました。忘れないようにノートしておこう。