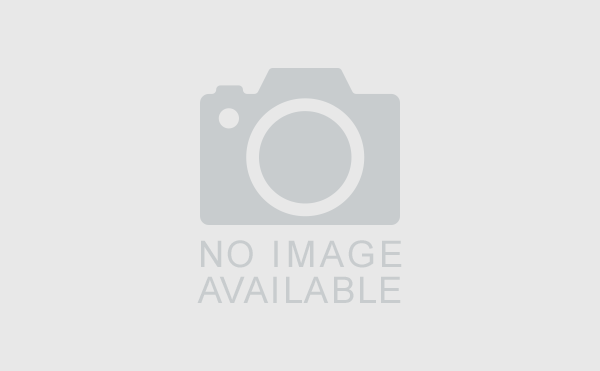道路陥没事故について地中レーダー探査の研究者の解説記事が出ていたのでクリップしておく
地中レーダー探査って専業としていないのではっきりしませんが、最近は廃れてる方向に動いていたような気がする。気のせいか?


ここでも写真にでてきたジオ・サーチさんの地中レーダー探査車なんですが、専業外の人間から言わせてもらえば、車載型地中レーダー探査はここの会社の一社独占のようなイメージがある。


久々に見ましたが、凸状の影がでると空洞があるとされる波形図です。
時速80kmで探査できるとあるのだから、高性能ではあると思うんですが、探査する時間よりも解析する時間の方が長いことかかっているのかも知れませんね。
三次元とかなんか昔カタログを見たような気がする。
AIにやってもらえば?なんて思うのですが、まあ部外者の私がこんなこと言ってるくらいなのでもう取り組んでいるのかもしれません。
一般的な日本の地質では地表面-2mまで探査できるとあるが、話題になった埼玉県八潮市のあの軟弱地盤では2mは出ないような気がする。
軟弱地盤では地中レーダー探査も苦労すると言う印象がある。


「通常の調査頻度で空洞発見は困難」、八潮道路陥没で探査の研究者が解説 | 日経クロステック(xTECH)
地中レーダー探査は、脳ドックと同じイメージがある。
脳ドックは3年に1回くらいやって、血管が変化したかどうかを重ねて判定していると理解している。
地中レーダー探査も一回やって異常なしではなくて、地中レーダー探査の解析データは再現性が有るはずなので、年1回くらいで実施して重ね合わせて変化を見るような解析手法をとった方がいいと思います。
(こんなの当たり前だと言われそうですが。)
硫化水素による下水管の破損が今回の陥没の主たる原因なのか私はすごく疑問を感じているので筋違いな話をするかもしれない。
シールドのセジメントってそんなに薄くないでしょう?このような陥没は、降雨による地表面から地中への浸透水が人孔周辺で発生し、周囲の地盤が吸い出されることが、主たる空洞の原因と今でも思っている。
あの陥没現場は下水管の管路が曲げられており、曲げられたところで管路の孔径が変わっているのであの辺りは大規模に開削工事を行ったはずである。
人孔以上に大きく開削工事をして人が埋め戻したようなところのため、空洞を生じさせやすい条件が揃ったと考えている。
まあ研究者でも専門家でもなんでもないので、他人事のただの落書きとしておきます。