読んで文字の通り「外様(とざま)」なのであるが、あるできあがった組織にあとから入り込むというのは、非常に難しいと言う話である。そもそも価値観からして違うのだから「言わずもがな」な話なのであるが・・・
例えば、会社の途中入社組なんてものは「外様」扱いだったりするわけだし、事務所の移動が少ない組織なら「異動してきた人」も外様になるのだと思う。
いや・・・人によっては、この組織を作り上げたプロパーな人以外は「外様」扱いなのかも知れないです。
わきまえずに虎のしっぽを踏むと、えらいことになるのだが・・・自分が今どこのポジションにいるのかというのは非常に見えにくいわけです。
外様はその組織では決して主人にはなれませんので・・・主人になりたければ自分で組織を作るしかないのです。
外様(とざま)とは、主君(上位権力者)を中心とした人間関係において、主君の親族・一門や累代にわたって仕えてきた譜第(譜代)と比較して疎遠にある者(家臣)を指す。
鎌倉幕府において実権を掌握した執権北条氏(特に得宗家)の直臣を御内人と呼んだのに対して、将軍と主従関係を持つ一般の御家人のことを指して「外様」と称した。御内人平頼綱と幕府御恩奉行安達泰盛との対立に端を発する霜月騒動は、御内人と安達氏を中心とする外様勢力との抗争としての一面を有した。
室町幕府においては、足利将軍家と元々関係が希薄であった守護大名(相伴衆や国持衆に列していない)を「外様衆」と称した。また、この頃から朝廷においても天皇との親疎によって譜代に相当する「内々」と「外様」に分類されるようになり、役職や宮中行事において格差を付けられたとされている。
また、南北朝や戦国の内乱を通じて、大名が周辺の有力な地頭や国人を自発的あるいは軍事的に取り込んでいく過程において、家臣団に編入された者たちも「外様」と称するようになった。
江戸幕府においては、関ヶ原の戦い後に徳川氏に臣従した上方衆と呼ばれる旧織田・豊臣系大名や地方の名門・旧家の大名を指して外様大名と称した。
一般的に、組織や機構に後から参加した個人や集団を「外様」と呼ぶことがある。この用法には、一定の差別的なニュアンスが含まれていると考えてよい。
「詰め方」のルールがわかればセンスはいらない! 寝る前につくる美しいお弁当
¥1,540 (2025年12月13日 08:35 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら商品価格と取扱状況は記載された日時の時点で正確で、また常に変動します。Amazon のサイトに表示された価格と取扱状況の情報は、この商品が購入されたその時のものが適用されます。)






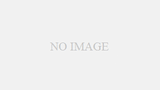
コメント